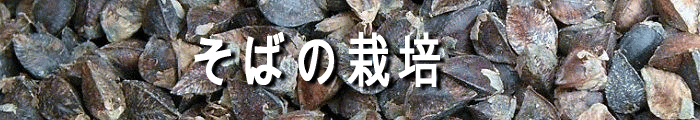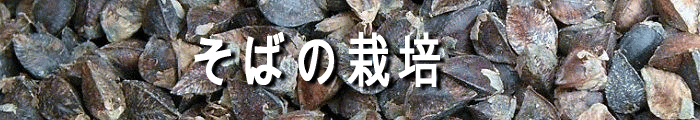.jpg) |
300坪、すなわち1反の畑で栽培したソバを10月28日に収穫。これを乾燥させるため畑に立てかけておいた。
まずは足踏み脱穀機を設置。立てかけておいたソバをここに集める。ここに集めるもひと苦労だ。 |
.jpg) |
足踏み脱穀機で実が辺りに飛び散らないように枠組みを作り、布をかぶせる。
|
.jpg) |
脱穀の作業手順
その1。まずは足踏み脱穀機でソバの実を取り出す。 |
.jpg) |
脱穀は能率を上げるために2人があたる。作業しやすいように補助が二人付いて、刈り取ったソバを渡す。すなわち2組で作業を行う。 |
.jpg) |
その2。足踏み脱穀機で取りだされた実だが、かなりまだ実がついて残っている。実を落とすため、さらに「からさお」でたたく。
その3。しかしそれでも実がまだついている。茎や葉をもんでさらに実を落としていく。
ここまでを1次脱穀作業と呼ぶことにする。 |
.jpg) |
次は第2次脱穀作業となる。
選別の作業になる。
第1次脱穀作業の段階では、実と葉や茎、さらにゴミが相当混じっている。大きなゴミをより分けるために大きな「ふるい」が登場。ネットで調べると「万石ふるい」とでもいうのだろうか。これも古くからある「ふるい」の一種だ。
大きなゴミが残って小さいソバの実がふるい落とされる仕組みだ。ここでざっと大きなゴミを取り除く。 |
.jpg) |
さらに選別のため細目のふるいでより分ける。 |
.jpg) |
選別作業のアンカーは「唐箕」でより分ける。風の力を利用して選別する。円筒形の風洞の中には扇板が取り付けられていて、手動でこの羽根を回転させ、風を起こし、上にある漏斗状の口からソバを入れていく。ソバは風力により選別され、重いソバの実は手前の一番口から、未熟な実は二番口から、ゴミや草は大口からと、それぞれの口から出てくる仕組みだ。 |
.jpg) |
この「唐箕」での作業は、だいたい二人で行い、一人は送風機を回し、もう一人はソバを落としていく。風をあまり強くすると良い実まで飛ばしてしまい、逆にあまり弱いと選別の状態が悪くなる。いつも下の口を見ながら風力を調節して回転させなければならない。
まさにその通り。わたしは強く回し過ぎて、よい実まで大口から飛ばしてしまったようで、もったいないので回収してさいど選別した。
脱穀を終えた実。まだまだゴミはあるが、これでまた一歩、新蕎麦に近づいた、そんな感じです。 |