 |
苗の購入
家庭菜園なら苗の購入が得策だ。スイカが好きな人でも5株あればいいのではないか。5株を植え付けると結構な面積を占める。ためにしスイカを作ろうと思えば1株から始めてもいいだろう。 |
 |
5月上旬に苗を購入。
小玉スカイと大玉スイカがある。小玉スイカのほうが栽培しやすいというのだが、それにこだわらず、作ってみたい品種を買ったほうが面白い。出来は二の次だ。わたしは両方の苗を買う。 |
 |
畑の準備
苦土石灰をまいてよく耕しておく。肥料は多肥がいいのか、少肥がいのかわからないでいるのだが、カボチャと同じく少肥でやっている。油かすまたはケイフンに化成肥料。控えめだ。
|
 |
定植
1メートル以上のウネに黒マルチを張る。
5月上旬に定植。防風と防寒のために、あんどん型のビニール囲い、またはビニールトンネル掛けをする。ビニールトンネルは高温になるため注意が必要だ。防虫ネットのほうが安全かもしれない。 |
 |
整枝・摘心
ツルが伸びるものには整枝・摘心が付きものだ。手引書を読んで学ぶ。一読しただけでは覚えられないし、身につかない。 以下は手引書からの抜粋である。
1) 親づるは摘心:親づるは本葉8〜10枚前後で先を切る。しばらくすると脇芽(子づる)が出てくる。その子づるの3本(4本でも可)を伸ばす。
2)孫づるは除去する:この子づるから出る脇芽(孫づる)はすべてとるが目標果(1子づる2果)が着果後は放任して良い。
|
 |
3)1、2番花は取る:雌花は子づるの7、8節ごとに着く。基本は1番花(5〜8節についた雌花)は取り、2〜4番目(12〜24節位)の雌花
に1番成りを着果させる。家庭菜園では梅雨時の着果不良も考え、1〜2番花に1番成りを着果させても良い。
しかし、基本は基本として、親ヅルを摘心し、子ヅルを3、4本残すまでは行うが、孫ヅルまでは手が回らない。あとは放任しておく。これでも実はなる。
|
 (160x120).jpg) |
人工授粉
手引書によると、1本の子ヅルから2個できるというのだから、1株で子づる3本だと、合わせて6個できることになる。
左が雄花、右が雌花。雄花の花粉を雌花につけてやる。
|
 |
これは一番目の雌花に着果。手引書によると摘除することになっているのだが、どうしようか。迷う。子ツルの10節以内には果実をつけてはいけないとあるので最初はそうしていたが、最近では放任だ。 |
 |
赤小玉スイカ「マダーボール」の赤ちゃん。着果した。ラグビーボールの形になるマダーボール。ベビーながらも成人の姿が想像できる。 |
 |
6月下旬のすがた。 |
 |
こちらは赤小玉スイカ「紅小玉」。 |
 |
収穫
授粉後に何日で収穫することがわかっているから、授粉の日付を書いておくとベストだ。ほかに収穫のタイミングを見る方法として、実の反対側にある巻ヒゲがすっかり茶色になった時を目安としている。当たる確率は高い。
7月下旬に「マダーボール」を収穫。満足感が伴う。やった!という感じだね。見た目がいい。 |
 |
問題は中身だ。不安を覚えながら包丁を入れる。思いっきりざくっと切る。緊張の一瞬だ。「お〜できている」。切り開くと色がまだ浅い。少し早すぎた、か。すぐに味見だ。口に入れると色に比べて甘い。できそこないであたりまえと覚悟していただけになんとなくひと安心。これからは収穫のタイミングを間違えないようにしなければならない。 |
 |
続いておなじ赤小玉の「紅小玉」。出来具合はどうだろうかと、「マダーボール」のうまさに少しばかり気をよくして包丁を入れる。
|
 |
こんどはぐっとスイカらしい鮮やかな赤色だ。「これはいい」。さっそく味見をする。見た目はいいのだが、マダーボールに比べて甘味がやや足りない。それにちょっと熟し過ぎている。こちらは収穫が少しばかり遅かったかなという感じだ。収穫のタイミングが難しい。 |
 |
冷やして塩をかけて食べた。冷やすと味がよくなる。自分が作ったスイカを食べるなんてとても贅沢だし、食卓が夏らしい彩りになる。
たたいてポンポンと澄んだ音がする間は収穫しないで、ボンボンと濁音になったら収穫のサインだという。この感覚がつかめない。 |
 |
こちらは黄大玉。これが収穫の最後で8月中旬だ。 |
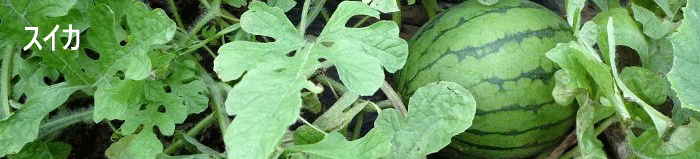






 (160x120).jpg)









